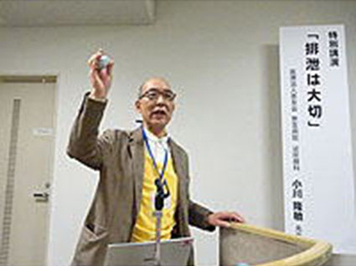第45回 排尿管理研究会

- 日時:
- 2020年1月26日(日) 13:00~17:00
- 場所:
- メルパルク京都
今回も寒い中、全国各地よりご参加いただき、有難うございました。また、今回メーカー様にも2社ご出展いただきました。御礼申し上げます。
一般講演
演題1.「急性期病院における排尿自立支援活動の実際」
講師 森つばさ 氏(康生会武田病院 看護師)
小児のCICケアの特殊性と注意すべき点など症例を交え、一人ひとりの成長に応じた指導法や地域・医師・看護師との連携の大切さを語っていただきました。
演題2.「骨盤底筋体操による尿もれ予防から、筋力増強による介護予防へ」
講師 舟谷文男 先生(産業医科大学 名誉教授)
演題3.「排尿自立指導がもたらした福井大学医学部附属病院の排尿ケアの変化 ~問題点と今後の活動に向けて~」
講師 天谷佳恵 氏(福井大学医学部附属病院 看護師)
演題4.「コ・メディカルで関わることによるCIC自立への有用性」
講師 植木敬子 氏(長野県立総合リハビリテーションセンター 看護師)
演題「前立腺肥大症に対する薬物療法」
講師 上田 朋宏 先生(医療法人朋友会 泌尿器科上田クリニック 院長)
演題「排泄は大切」
講師 小川隆敏 先生(医療法人恵友会 恵友病院 泌尿器科)
特別講演
「前立腺肥大症に対する薬物療法」

講師 上田 朋宏 先生(医療法人朋友会 泌尿器科 上田クリニック 院長)
■前立腺肥大症を始めとした排尿関連の病気について ・男性・女性共に多く見受けられる症状 ・「排尿自立」という言葉を使用することについて 世間が排尿などに関心を持ち始めた ・前立腺肥大症の症状 夜間頻尿 200~400程溜められるか否かは余り関係無い ・ICS 排尿筋収縮の異常 過活動膀胱 客観的ではなく、患者の満足度を大切に ↓ 原因は、前立腺肥大だけではない→症状を軽減させるための薬物療法 診察のイメージ年齢は関係なく、誰にでも起こる症状 生活指導が重要 年々、尿漏れの症状を訴える患者が増加してきている ■治療内容 ・内視鏡は尿道造影が非常に分かりやすい ・膀胱容量を増やすだけではなく、前立腺肥大の症状緩和も併行して治療 ・副交感神経と交感神経のバランスで膀胱を動かしている 膀胱に対する神経支配 ・患者が持つ症状の複雑さ(症状・病気は患者一人につき一つではない) ・検尿・残尿測定(院長自身の検査方法) ・安い・正確な治療を目指して ・排尿障害に対してどのように接していくか ・バルーンを使用している場合、治療がさらに難しくなる メンタル面ですぐトイレに行こうと判断する患者が多い ↓ 頻尿の症状を訴える患者の多くは、極力水分を取らないようにすることが多い ↓ しかし水分を制限してしまうと余計膀胱に負担がかかり、体に悪影響を及ぼす ↓ さらに、症状が悪化する ・当院では水分を多く摂取することを推奨している ・骨盤底筋体操も症状緩和の助けになる場合がある
「排泄は大切」

講師 小川隆敏 先生(医療法人恵友会 恵友病院 泌尿器科)
■脊損の膀胱と排尿自立指導について ・岩坪先生から学ぶ→膀胱造影が脊損の尿路管理で一番大切 ・膀胱の変形が尿路管理に関連 CICが出来ない場合はカテーテルなどを使用 ・腎臓を守ることが重要 尿路管理のガイドライン発行 ・尿流動体検査→危険因子が有るか無いかを判断する ・最大膀胱容量が少ない又は、収縮があまりない場合や膀胱が上手く開かない場合もある ・脊損の麻痺など検査→なかなか現場で何回も検査することは難しい ・CMG(膀胱内圧測定)やVCG(排尿時膀胱尿道造影)などの検査方法がある ・排尿の命令→膀胱の活動(過活動・低活動・無収縮・髄収縮)の4つに分けられる ・合併症を起こす患者もいる→過活動膀胱よりも無収縮の方が合併症を引き起こしやすい ・尿道の開き具合が残尿率と一致→膀胱の活動状況がよく分かるようになった ・膀胱コンプライアンス→尿が溜まれば溜まるほど膀胱内の圧力がかかる ・膀胱機能は、膀胱の活動に大きく関わっている ・排尿筋は、膀胱の変形や異常な収縮などを引き起こしかねない ・事故により、脊損で膀胱の活動や機能の低下などの異常が出てくる ・膀胱の開きや排尿筋の収縮が上手くいかない場合、指圧や腹圧などを推奨 ・ガイドラインに沿った症状や病気の治療方法だけでは、患者の負担が減少しない ・患者一人一人に合った治療方法を見出すことが大切である ・排泄チームを作る→週に一回カンファレンス→患者の最新の状態を常に把握 ・患者や患者の家族に対して、未だはっきりとした排尿問題と自立支援の解決方法を即座に提案出来る段階ではない ・排尿問題さえ解決出来れば、患者自身や家族の負担も減少するが実際は難しい ・患者のことを第一に考えると自宅で排尿自立が出来るように最大限考慮することが重要 ・触診残尿感、50代以上の残尿感測定は難しい ・導尿からの痛み→便が溜まり、尿が出ないこともある ・排尿時の痛みが治療でもあまり改善しない場合は、手術を受けてもらうこともある ・CV検査→膀胱の収縮を見る→自然排尿への道 ■排尿関連の病気に関連して ・様々な知識と経験が患者に全て影響していく ・多職種連携は難しいが重要である ・患者の負担を極力減らす工夫が必要